※当サイトは記事広告・アフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
・社労士試験は短期合格が可能なのだろうか?
・社労士試験は働きながらでも合格できる?
・社労士試験に合格するにはどんな勉強方法がいい?
社労士試験に合格するためには、800~1,000時間程度の勉強時間が必要と言われます。
1,000時間を1年(52週)で割った場合、おおよそ週20時間の勉強時間が必要です。
平日2時間、休日5時間など、働きながらでも1年以内の短期合格を目指すことは可能です。
社労士の短期合格を目指すメリット
社労士試験の合格率は、年によって増減はありますが、約6~7%が平均です。
試験の難易度は高く、合格するまでの平均受験回数は3~4回程度と言われています。
だからと言って初学者が1年以上かけてスケジュールを組むのは合理的ではありません。
私は1年以内の短期合格を目指すべきと思っています。
①モチベーションが維持しやすい
・合格率6%、勉強1,000時間は、初学者にとって途方もない数字
・短期合格は無理そうだから、1年以上かけて計画しよう
このように考える方もいるでしょう。
しかしながら、1年以上の計画がスムーズに進むでしょうか。来年の試験が本番と思ってしまうと、ついついさぼってしまうことがあるでしょう。
1年以内のスケジュールを立てたほうが、進捗管理ができて、モチベーションの維持がしやすいと実感しています。
私の場合、試験まであと3ヶ月で模試はD判定(涙)
それまでは停滞期でモチベーションが下がり気味でしたが、危機感を感じて、勉強時間を増やすことができました。
②社労士試験は運の要素がある
私が社労士試験を受ける際、先輩合格者から言われたのは、「社労士試験の選択式は運要素が強いけど、択一式で不合格になるのは実力不足、勉強不足」というアドバイスでした。
社労士試験は各科目のうち、総得点が一定以上なければならないのと同時に、科目ごとの得点も基準点以上なければなりません。1科目でも基準点を下回ってしまうと、いくら総得点が高くても、その時点で不合格となってしまいます。
択一式では各科目10点満点中4点以上取らなければならず、選択式では各科目5点満点中3点以上取らなければなりません。
選択式では、出題箇所によって正答率が低くなってしまうことがあります。その場合は補正(救済)制度があります。
選択式の出題箇所、補正(救済)制度によって合格できるか変わってくることから、運要素が強いと言えます。
一方で択一式は1科目10問、1問で文章形式の5肢から正答を選びます。
7科目×10問×5肢=350肢を読み込むことから、勉強量に比例して合格に近づきます。
そのため私は、選択式は自分の運の良さを信じることとして、択一式が合格ラインまで持っていけるよう勉強のスケジュールをたてました。
選択式の足切りに泣かされ、何度も試験を受けるうちにモチベーションの維持が難しくなってきて諦めてしまう方もいることでしょう。
実際に私は令和3年度の試験で、選択式が労働一般1点、国民年金2点でしたが、どんぴしゃの補正(救済)制度によって合格することができました。
自分の運を信じてよかったです!
このように社労士試験は短期合格を目指すメリットが大きいです。
そのためには択一式を確実に合格ラインまで持っていくことが重要となります。
働きながら短期合格するには通信講座がおすすめ
日商簿記2級や中小企業診断士を独学で合格した経験から、まずは同じように独学でやってみようと市販のテキストと問題集を使って勉強を始めました。
テキストをさらっと読み、問題集を繰り返すアウトプット中心の勉強方法です。
しかしながら社労士は科目横断的な論点などがあり、途中でインプットも重要と気付かされ、通信講座を活用しました。
最初は市販のテキストを使っていましたが情報量が限られること、独学では不明点が聞けないことなど、なかなか理解が進まないもどかしさを感じていました。
そのため、途中から通信講座に申し込み、テキストと動画講座でインプットしたところ、一気に理解が進むことができるようになりました。
動画講座では講師が口頭で伝えてくれるため、テキストベースよりも多くの情報を得ることができます。
多くの受験生が悩むポイントなど、テキストを深堀して伝えてくれます。
また通信講座は不明点を質問ができるため、1人で悩むことがなくなります。
このように社労士試験は独学でも不可能ではありませんが、働きながら短期合格を目指すなら、効率よくインプットできる通信講座がおすすめです。
私の勉強仲間の友人の何人かは、通信講座「スタディング」で勉強していました。
働いていてじっくり勉強時間を取れない場合でも、スキマ時間を利用して、勉強することができます。

私が実践した短期合格の勉強方法
①スケジュールを立てる
私は勉強を始めた際に8か月で合格点まで持っていくため次のスケジュールを立てました。
→以下は実際の進捗状況です。
市販のテキストと択一式の問題集を一通り終わらせる。理解できているかは気にしない。
→労働・社会保険一般以外の科目を何とか年内に問題集を一通り完了。労働・社会保険一般までは手が回らないと実感して、他の科目を優先する。
繰り返し択一式の問題集を解く。5回転くらいする。
→アウトプット中心に、問題集を1科目1週間で進める。
アウトプット中心に問題集を解いて知識を定着しようとするも、3回転くらいしても同じところで何度もつまずく。
インプットができていないと判断して、通信講座を受講する。
GWや休日に模擬試験や過去問を本番形式で解き、自分の実力を計るともに、試験の時間配分に慣れる。
→市販の模試試験を解くも合格圏に達せず、危機感を感じて勉強のペースを上げる。
選択式、法改正を含めて繰り返し問題集を解く。
→選択式対策を始める。何とか択一式が勝負できるくらいの実感を得る。
②繰り返し問題集を解く
一問一答式の問題集と5肢択一式の問題集を併用しました。
一つ一つの選択肢の正誤を理解しないと知識が定着していかないため、最初の内は一問一答形式の問題集を何度も解くことが重要です。
時間がかかりますが、選択肢一つの文章一言一句を読み込むため理解が深まります。
一方で、5肢択一式は本番と同じ出題形式です。5肢の中から正解又は不正解を選ぶ、正解の個数を選ぶなど、本番の出題形式に慣れることが重要です。
③定期的にテキストや動画でインプットする
これまでも述べたように社労士試験では、法律の条文一語一句、数字など、細かいところまで覚えておく必要があり、インプットが非常に重要となります。
私は問題集で間違えた箇所をテキストに戻って、テキストに間違えた内容を赤字で書いていました。
全科目問題集1周した後にテキストを通読してインプットする。その場合には赤字で書いてある間違えた箇所を意識することができます。
苦手と思う箇所はテキストだけでなく、動画を何度も見返して、知識を定着させました。
試験のときには講師が説明していた場面ごと思い出すことができました。
④模試を解く
社労士試験の時間は、午前中が選択式で1時間20分、午後が択一式で3時間30分と長いため、集中力と体力が必要です。
長い試験時間ですが、解答に手間取っているとあっという間に時間が過ぎてしまい、時間配分が非常に重要になります。
試験と同じ時間で何度か模試を解いて、時間配分など試験に慣れておくことが有効です。
本番の試験では午後の択一式で最初の科目の労基で想定以上の時間を取ってしまい、最後の問題を解いたのは試験終了ギリギリでした。
模試で時間配分の練習をしていたので、途中からこのままでは間に合わないと問題を解くペースを上げることができました。
【まとめ】社労士試験は短期合格を目指すのがおすすめ!
社労士試験は出題範囲が広くて難しいですが、スケジュールを立てて勉強をすれば、1年以内の短期合格が可能な資格です。
しかし、日々の仕事や家庭のことがあり、勉強との両立がついついおろそかになってしまいがちです。
通信講座を利用すれば講師のサポートがあるため、勉強のモチベーションも維持するのに有効でしょう。
通信講座利用も視野に入れて短期合格を目指してみてはいかがでしょうか!




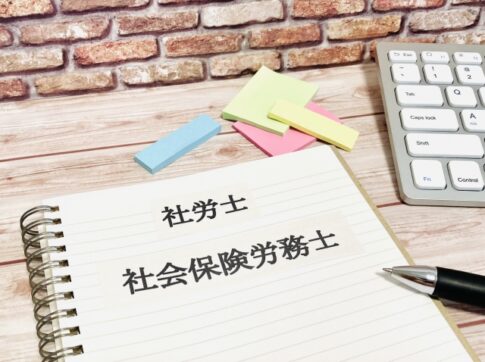



私自身、11月中旬から勉強を始めて約9か月で合格しました。
平日は帰宅後2時間、土日は5時間勉強し、直前期には勉強時間を増やして平日3~4時間、土日は5~10時間になりました。
総勉強時間は約700時間ですが、働きながら何とか確保できる勉強時間でした。